【税理士監修】投資信託は相続税の対象!相続税評価額の計算方法や引き継ぐための相続手続きも解説
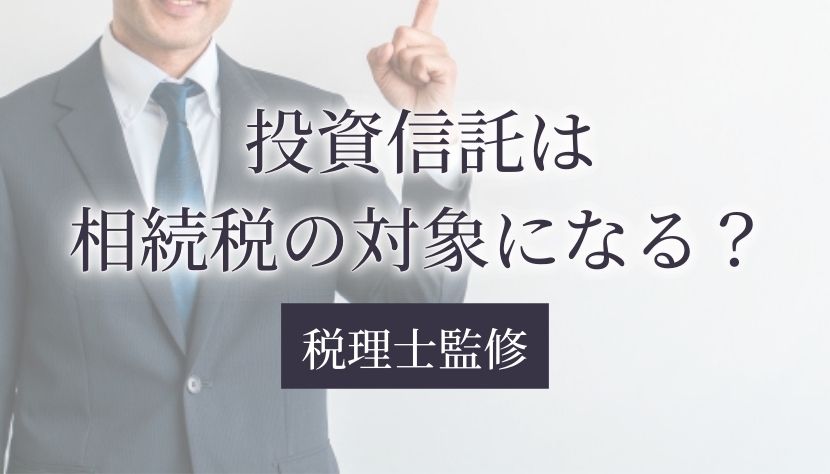
投資信託は相続税の対象で、被相続人が投資信託を所有していたときは相続税がかかる場合があります。
投資信託を相続したら相続税評価額を計算し、相続財産として扱わなければなりません。
本記事では、投資信託の相続税評価額の計算方法や、引き継ぐための相続手続きを解説します。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
投資信託を相続したら相続税がかかる
投資信託とは、投資家から集めたお金を投資の専門家が運用し、得られた利益を投資家に分配する金融商品のことです。
投資信託を含め、経済的価値があるものはすべて相続税の対象になるため、被相続人が投資信託を所有していたときは相続税がかかる場合があります。
よって、投資信託を相続したら相続財産として取り扱い、相続税評価額を計算します。
投資信託の相続税評価額の計算方法は後ほど解説します。
<ポイント!>
相続税評価額とは、相続税を計算するための財産の価額のことで、財産の種類によって計算方法が決められています。
前提として、相続税は相続財産の合計額に対してかかるため、財産の種類(たとえば、現金、建物、土地、投資信託など)ごとに相続税評価額を計算し、相続財産の合計額を求める必要があります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
今すぐ税理士に相談したい場合は、税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

相続した投資信託の種類を調べる方法
投資信託の相続税評価額の計算方法は一律ではなく、以下の種類ごとに異なります。
| 1.日々決算型投資信託=毎日決算が行われる投資信託 2.上場投資信託=金融商品取引所に上場している投資信託 3.1と2以外の投資信託(一般投資信託)※本記事では「一般投資信託」と呼ぶ |
相続した投資信託の種類がわからない場合は、取引報告書、残高証明書、目論見書(投資信託の説明書のようなもの)などを確認するか、取引先の金融機関に問い合わせましょう。
なお、日々決算型投資信託でなく上場投資信託でもない上記3(一般投資信託)が一般的ではあります。
<例>
・MRF(=日々決算型投資信託)
・外貨建てMMF(=日々決算型投資信託)
・ETF(=上場投資信託)
・REITまたはJ-REIT(=上場投資信託)
投資信託の相続税評価額の計算方法
ここからは投資信託の相続税評価額の計算方法を解説します。
先述の通り、相続した投資信託の種類によって異なります。
| 1.日々決算型投資信託 2.上場投資信託 3.1と2以外の投資信託(一般投資信託) |
<注意!>
外貨で運用する外貨建て投資信託の場合は、円に換算する必要があります。
外貨から円に換算するときに使う為替レートはTTBレートです(※円から外貨に換算するときはTTSレート)。
被相続人が死亡した日が休日の場合は為替レートが公開されていないため、被相続人が死亡した日に最も近い日の為替レートを使います。
1.日々決算型投資信託
日々決算型投資信託(MRF、外貨建てMMFなど)の相続税評価額は、以下で計算します。
| 被相続人が死亡した日の1口あたりの基準価額(1円が基本)×口数+再投資されていない未収分配金-未収分配金に対する源泉徴収されるべき所得税の額(未収分配金×20.315%)-信託財産留保額・解約手数料=日々決算型投資信託の相続税評価額 |
複雑な計算に見えますが、MRFの場合は「被相続人が死亡した日の1口あたりの基準価額×口数」が相続税評価額になる場合が多いでしょう。
理由として、現在は利回りが低いことから「再投資されていない未収分配金」「未収分配金に対する源泉徴収されるべき所得税の額(住民税・復興特別所得税含む)」は0円に近く、また「信託財産留保額・解約手数料」も設定されていない傾向にあるためです。
ただし、外貨建てMMFの場合は利回りが高く、未収分配金があるかもしれないので、取引先の金融機関に問い合わせましょう。
1口あたりの基準価額と口数は残高証明書で確認できます。
2.上場投資信託
上場投資信託(ETF、REITまたはJ-REITなど)の相続税評価額は、以下で計算します。
| 1口あたりの価格×口数=上場投資信託の相続税評価額 |
1口あたりの価格は、以下の中で最も低い価格を使います。
| 1.被相続人が死亡した日の最終価格(=終値) 2.被相続人が死亡した月の最終価格の月平均額 3.被相続人が死亡した月の前月の最終価格の月平均額 4.被相続人が死亡した月の前々月の最終価格の月平均額 |
残高証明書で確認できる場合がありますが、記載されていなければインターネットで調べることもできます。
<1口あたりの価格の調べ方>
| 1.被相続人が死亡した日の最終価格 | Yahoo!ファイナンス |
| 2.被相続人が死亡した月の最終価格の月平均額 3.被相続人が死亡した月の前月の最終価格の月平均額 4.被相続人が死亡した月の前々月の最終価格の月平均額 | 日本取引所グループ(月間相場表) |
なお、被相続人が死亡した日が休日の場合は価格が公開されていないため、被相続人が死亡した日に最も近い日の最終価格を使います。
また、祝日や連休の影響で最も近い日が2日ある場合は、2日間の最終価格の平均額を計算します。
<例>
| 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 |
| 価格15,000円 | 公表なし | 価格15,500円 |
| 最も近い日 | 相続発生日 | 最も近い日 |
(15,000円+15,500円)÷2=15,250円
3.1と2以外の投資信託(一般)
一般投資信託(日々決算型投資信託と上場投資信託以外)の相続税評価額は、以下で計算します。
| 被相続人が死亡した日の1口あたりの基準価格×口数-被相続人が死亡した日に解約した場合の源泉徴収されるべき所得税の額(被相続人が死亡した日に解約した場合の※譲渡所得×20.315%)-信託財産留保額・解約手数料=一般投資信託の相続税評価額 |
※譲渡所得=被相続人が死亡した日の1口あたりの基準価格×口数-取得費(投資信託の購入価格)
「信託財産留保額・解約手数料」は設定されていない場合が多いでしょう。
1口あたりの基準価格と口数は残高証明書で確認するか、基準価格はインターネットで調べることもできます。
<1口あたりの基準価格の調べ方>
インターネットで投資信託の銘柄で検索し、投資信託の運用会社または証券会社のホームページで確認するか、投信総合検索ライブラリーで検索します。
注意点として、一般的に1万口あたりの基準価格が記載されているため、1口あたりの基準価格を求める必要があります(基準価格÷1万)。
また、被相続人が死亡した日が休日の場合は価格が公開されていないため、被相続人が死亡した日より前の最も近い日の基準価格で計算します。
投資信託を相続するときの注意点
投資信託を相続するときは、以下3点に注意しましょう。
投資信託の価格は変動する
投資信託は価格が変動するため、被相続人が死亡した日、遺産分割協議をした日、実際に相続手続きをする日、などで価格が大きく変わる可能性があります。
予想外に価格が変動すれば相続人同士でトラブルが起こりかねないため、複数の相続人がいる場合は対策が必要です。
具体的には、投資信託を解約・売却して現金化してから分割したり、遺産分割協議書に遺産分割協議の時点の相続税評価額で分割する旨を記載したり、などが有効でしょう。
所得税がかかる場合がある
相続した投資信託を解約・売却して利益を得た場合は、譲渡所得として所得税がかかることを覚えておきましょう。
ただし、被相続人が死亡した日の翌日から3年10か月以内の解約・売却であれば、取得費加算の特例を使える場合があります。
取得費加算の特例とは、相続した財産を先述の期間までに譲渡すると相続税の一部を取得費に加算できる制度で、取得費が増える(=譲渡所得が減る)ことで所得税の負担を軽減できます。
なお、相続税にも特例や控除があるため、相続税がかかる場合は税理士に相談してみましょう。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

未払分配金も相続財産として扱う
そもそも分配金とは、決算ごとに投資信託の運用によって得た利益の一部を投資家に分配するお金のことです。
被相続人が分配金を受け取ることが確定していたものの、受け取る前に死亡した場合の分配金を「未払分配金」と呼びます。
未払分配金は、本来であれば被相続人が分配金として受け取っていたものであるため、相続財産として取り扱う必要があります。
見落とさないように注意しましょう。
投資信託を引き継ぐための相続手続き
投資信託を相続するときは、主に以下の手順で手続きを進めましょう。
金融機関によって異なる場合がある点に留意してください。
| 1.取引先の金融機関に相続が発生した旨を伝える 2.金融機関で相続が発生した日の残高証明書を取得する 3.遺産分割協議をして遺産の分け方を決める 4.取引先の金融機関で相続人の口座を開設する 5.金融機関に必要書類を提出する 6.相続手続きが完了する |
被相続人の名義のままでは投資信託の解約・売却ができないため、一度は相続人の名義の口座に引き継ぐ必要があります。
注意点として、被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座に引き継ぐことはできません。
相続人の通常の口座に引き継がれ、被相続人が死亡した日までの利益が非課税になります。
投資信託を相続したときの相続税申告書の書き方
以下に当てはまる場合は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。
・相続税がかかる場合
・相続税の特例を適用する場合
相続税申告書の様式や書き方は国税庁のホームページで公開されているため、詳しく見たい方は確認するとよいでしょう。
相続税の申告書等の様式一覧(令和6年分用)
相続税の申告書の記載例
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

【Q&A】投資信託の相続に関するよくある質問
最後に、投資信託の相続に関してよくある質問にお答えします。
相続した投資信託の取得価額とは?
相続した投資信託の取得価額とは、投資信託の購入価格のことで、被相続人から引き継ぎます。
取引報告書などでも確認できます。
投資信託にかかる相続税の計算方法は?
相続税は、投資信託を含めた遺産総額が基礎控除額を超えた場合にかかります。
相続税を計算するときの手順は以下の通りです。
| 1.課税価格を計算する 2.課税遺産総額を計算する 3.相続税の総額を計算する 4.各法定相続人の相続税額を計算する 5.各法定相続人の納税額を計算する |
相続税がいくらくらいかかるかを正確に知るには、税理士へ相談する必要があります。
相続した投資信託を解約したら確定申告が必要?
相続した投資信託を解約して利益を得た場合は、原則として確定申告をする必要があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で取引していた場合は、原則として確定申告をする必要はありません(損益通算や繰越控除を行う場合は必要)。
投資信託の相続や相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ

・何が相続税の対象になるかわからない
・相続税がかかるかわからない
・相続税がいくらかかるか知りたい
・相続税を減らすにはどうしたらよいか
などのお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください!
投資信託をはじめ評価が複雑な財産がありますが、相続税評価額は相続税の基準になるため、正確に計算しなければなりません。
同時に、相続税の負担を減らすためには相続税対策の検討も必要です。
当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、長年の経験と最新の知識を活かした相続税対策を強みに、相続税の申告まで一貫してサポートいたします。
できる限りお客様の負担を軽減できるよう個別にご提案いたしますので、相続に不安がある方も安心してご相談ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続の手続きやお悩みにも幅広く対応可能です。
相続税のご相談は初回無料でお受けしていますので、些細なことでもまずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所の相続に関する業務の詳細はこちらから
お見積り・ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから
\相続税のご相談は初回無料で承っております/

まとめ
投資信託の相続税評価額の計算方法は、相続した投資信託の種類によって異なります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えなければ、相続税がかかることはありません。
相続財産の合計額を求めるにはすべての財産を個別に評価する必要があるため、無理をせず、困ったときは税理士に相談することをおすすめします。
