【完全版】サラリーマン(会社員)の節税対策を税理士がわかりやすく解説!
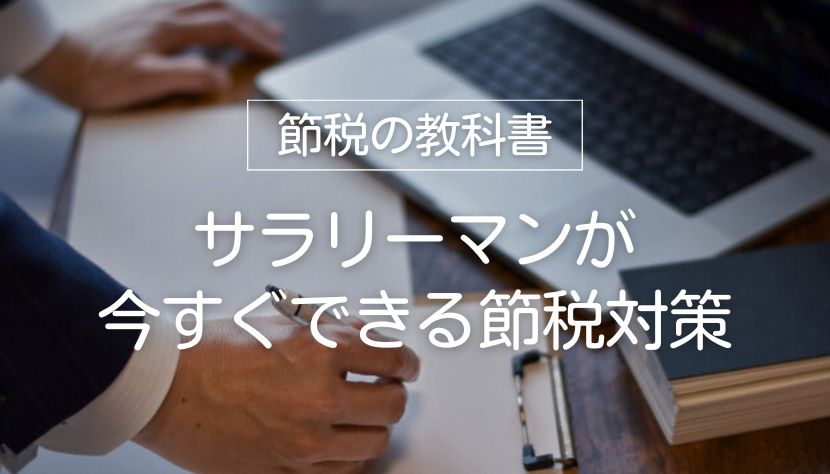
給与から多額の税金や社会保険料が差し引かれ、「少しでも手取りや増やす方法はないのか」と悩まれているサラリーマン(会社員)の方が少なくありません。
一見、サラリーマンは節税の余地が少ないように思えますが、正しい知識を身につけることで想像以上に節税効果を得られる場合もあります。
本記事では、サラリーマンが今すぐできる節税対策をわかりやすく解説します。
また、不動産投資や会社設立による節税にも触れているので、興味がある方はぜひお役立てください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
節税対策とは
節税対策とは、「税法の範囲内で税金の負担を軽減させる手段」のことです。
合法的かつ効果的な方法を取り入れることで余計な税金を支払わずに済むため、手取りが増やせます。
ただし、税法の範囲を超えた節税対策は「脱税」に当たり、意図的ではなくてもペナルティが課されるので注意が必要です。
正しい方法で節税できるよう、節税対策への理解を深めましょう。
会社員が支払う税金の種類
会社員が給与から差し引かれる税金は、「所得税」と「住民税」の2種類です。
このうちの所得税は、個人の所得から「所得控除」を差し引いた金額に税率を適用して計算されます。
適用される税率は所得が多いほど上がるため、節税するには控除制度を利用して課税の対象となる所得を小さくすることが重要です。
サラリーマンが今すぐできる11の節税対策
最初にご紹介するサラリーマンの節税対策一覧は、以下の通りです。
| 1.扶養控除 2.配偶者控除 3.医療費控除 4.セルフメディケーション税制 5.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 6.生命保険料控除 7.地震保険料控除 8.特定支出控除 9.iDeCo(個人型確定拠出年金) 10.NISA(少額投資非課税制度) 11.ふるさと納税 |
順に、わかりやすく解説します。
1.扶養控除
扶養控除とは、親や子など対象となる扶養親族がいる場合に利用できる控除制度です。
対象となる扶養親族は、その年の12月31日時点で以下の要件をすべて満たす方に限られます。
| ・配偶者以外の親族、里子、市町村長から養護を委託された老人であること ・納税者と生計を一にしていること ・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は収入が103万円以下)であること ・青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと |
なお、扶養控除の控除額は以下の通りです。
扶養親族の年齢や同居の有無で、控除額が変わります。
【扶養控除額】
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 扶養対象扶養親族 (原則16歳以上の方) | 38万円 |
| 特定扶養親族 (19歳以上23歳未満の方) | 63万円 |
| 老人扶養親族 (70歳以上の方) | 同居している場合48万円 上記以外の場合58万円 |
※その年の12月31日時点での年齢
一般の控除対象扶養親族とは、16歳以上の方、または非居住者の扶養親族で以下のいずれかに当てはまる方を指します。
| ・16歳以上30歳未満の方 ・70歳以上の方 ・30歳以上70歳未満で、以下のいずれかに当てはまる方 1.留学により国内に住所・居所を有しなくなった方 2.障害者の方 3.あなたからその年の生活費または教育費の支払いを38万円以上受けている方 |
※その年の12月31日時点での年齢
また、老人扶養親族の入院によって別居状態の場合は、たとえ1年以上の長期入院でも同居として取り扱います。
ただし、老人ホームへ入所している場合は同居に認められません。
国税庁:扶養控除
2.配偶者控除
配偶者控除とは、対象となる配偶者がいる場合に利用できる控除制度です。
対象となる配偶者は、その年の12月31日時点で以下の要件をすべて満たす方に限られます。
| ・民法の規定による配偶者であること ・納税者と生計を一にしていること ・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること ・青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと |
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額や配偶者の年齢によって異なり、配偶者がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は表右側の控除額が適用されます。
| 納税者の合計所得金額 | 控除額 (一般控除対象配偶者) | 控除額 (老人控除対象配偶者) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
国税庁:配偶者控除
3.医療費控除
医療費控除とは、1年間(その年の1月1日~12月31日)の医療費が一定の金額を超えた場合に利用できる控除制度です。
なお、同一生計の配偶者または親族のために負担した費用も含められます。
対象となる主な医療費は、以下の通りです。
| ・病院の診療費・治療費 ・入院費・手術費 ・義足や補聴器など治療に必要な医療器具の購入費 ・通院のための交通費 ・子どもの歯列矯正費 ・処方せんによる医薬品の購入費 など |
医療費控除の控除額は、以下で計算します。
| 医療子控除の控除額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円(※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%) |
最大200万円の控除が受けられるため、大幅に節税できるケースもあります。
未払いの医療費がある場合、実際に支払った年の医療費控除の対象となる点に注意しましょう。
国税庁:医療費控除
4.セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、薬局やドラッグストアなどで市販される対象の医薬品を購入した費用が1年間で12,000円を超えた場合に利用できる医療費控除の特例です。
同一生計の配偶者または親族のために購入した費用も含められ、最大88,000円の控除を受けられます。
ただし、一定の健康診査や予防接種などを行なっている方にしか適用されない点と、医療費控除との併用ができない点には注意しましょう。
なお、当初は令和3年度分までが対象でしたが、改正により、税制対象医療品を、より効果的なものに重点化(令和4年分からは効果が薄いものは対象外とし、とりわけ効果があるものの対象を拡充)したうえで、令和8年度分までに延長されました。
5.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入したりリフォームしたりする場合に、一定の要件を満たすと利用できる控除制度です。
一般的には「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と呼ばれています。
控除率は年末残高等の0.7%と一律で、控除期間は最長13年です。
ただし、控除を受けるための要件が細かく設定されており、また住宅の区分や住み始めた時期によって借入限度額や控除限度額にも差があります。
住宅の購入・リフォームを予定している場合は、事前に詳細を確認することをおすすめします。
6.生命保険料控除
生命保険料控除とは、「生命保険料」だけでなく「介護医療保険料」や「個人年金保険料」を支払っている場合にも利用できる控除制度です。
ただし、加入している保険の内容によって対象外となる場合があるため、事前に確認する必要があります。
生命保険料控除額は最大120,000円で、保険の契約日に基づいて以下の通りに計算します。
【新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
【旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
国税庁:生命保険料控除
7.地震保険料控除
地震保険料控除とは、納税者や同一生計の配偶者または親族が所有する「建物」・「家財」を対象とした地震保険料を支払っている場合に利用できる控除制度です。
なお、「常時その居住の用に供する家屋や生活に通常必要な動産(家具や30万円以下の貴金属など)」に限られるため、空き家や別荘など居住用ではない建物は控除の対象になりません。
地震保険料控除額は、以下の通りです。
【地震保険料控除額】
| 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 |
国税庁:地震保険料控除
8.特定支出控除
特定支出控除とは、サラリーマンが自腹で支払った特定支出の合計額が「給与所得控除額」の半分(最高125万円)を超える場合に、超えた部分に対して利用できる控除制度です。
特定支出として認められる費用には、以下が挙げられます。
| ・通勤費 ・転居費 ・研修費 ・資格取得費 ・帰宅旅費 ・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など) |
サラリーマンの場合、仕事上必要であればスーツ代や本代なども勤務必要経費として認められる場合があります。
ただし、特定支出控除を利用する際は給与の支払者による証明が必要です。
国税庁:特定支出控除
9.iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは、個人型の確定拠出年金で、老後に向けた資産形成を目的として個人で資産を運用する制度です。
運用する金融機関や運用商品を自分で選び、毎月掛け金を積み立てて60歳まで運用します。
掛け金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になり、運用益も非課税になるため、大きな節税効果が期待できるでしょう。
また、給付額を受け取る際も「公的年金等控除」または「退職所得控除」を利用できます。
実際にどれくらいの節税効果を得られるのか、iDeCoのシミュレーションを試してみるのもおすすめです。
かんたん税制優遇シミュレーション
iDeCo公式サイト
10.NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは、NISA口座内で投資した金融商品によって得た利益(売却益・配当・分配金)が非課税となる「少額投資非課税制度」です。
本来であれば、金融商品への投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISAは利益の満額を受け取れます。
また、2024年より非課税保有期間が無期限になったため、長期で資産形成に取り組むことができます。
興味のある方は、NISAのつみたてシミュレーションを試してみるとよいでしょう。
つみたてシミュレーター
NISA公式サイト
11.ふるさと納税
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付することで返礼品を受け取れる制度です。
寄付金には「寄附金控除」が適用され、寄付した金額のうち2,000円を超える部分で所得税と住民税の控除が受けられます。
実際に手元からお金が出ていき、その分が控除され、返礼品を受け取れるという仕組みのため、厳密には節税対策というよりお得な制度です。
ただし、住んでいる自治体以外に納税することから、場合によっては住んでいる自治体が税収減となる問題もあります。
また、控除限度額が設定されているので、むやみやたらに寄付せず、限度額を把握することも重要です。
控除限度額の目安は、ふるさと納税ポータルサイトの表や寄附金控除額の計算シミュレーションでも簡単に確認できます。
ふるさと納税ポータルサイト:税金の控除について
特定のケースでサラリーマンが利用できる控除制度
次に、サラリーマン(会社員)が状況に応じて利用できる控除制度を解説します。
自分が該当する制度があるかどうか、確認してみましょう。
配偶者と離婚・死別した場合
配偶者と離婚や死別した後に再婚していない場合は、「ひとり親控除」または「寡婦控除」の対象です。
ひとり親控除
令和2年分より「寡夫控除」から「ひとり親控除」に変更されました。
ひとり親控除は女性と男性ともに適用があり、未婚、死別・離婚後に再婚していないまたは配偶者の生死が不明かつ下記の要件をすべて満たす方に適用されます。
| ・婚姻関係と同様の状態と認められる相手がいないこと ・子どもと同一生計であること(※子どもとは総所得・金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族ではない場合に限る) ・合計所得金額が500万円以下であること |
なお、控除額は35万円です。
国税庁:ひとり親控除
寡婦控除
「ひとり親控除」の要件に該当せず、合計所得金額が500万円以下で①または②の要件を満たす女性は「寡婦控除」が適用されます。
| ①夫との離婚後に再婚しておらず、子以外の扶養親族がいる ②夫との死別後に再婚していない、または夫の生死が不明 |
婚姻関係と同様の状態と認められる相手がいる場合は、控除が適用されないことを理解しておきましょう。
なお、控除額は27万円です。
また、男性は子を有する要件があるなどの「ひとり親控除」の適用だけであり、女性が受けられる「寡婦・ひとり親控除」よりは、受けられる範囲が狭いのも特徴です。
国税庁:寡婦控除
災害・盗難の被害を受けた場合
災害や盗難により特定の資産に被害を受けた場合は、「雑損控除」が適用されます。
特定の資産とは、住宅や家財、衣服など生活に必要な資産のことです。
なお、合計所得金額が1,000万円以下の方は、「雑損控除」または「災害減免法による税金の軽減・免除」のどちらか有利なほうを選択できます。
国税庁:雑損控除
株取引で損をした場合
上場株の取引で損失が発生した場合は、「損益通算」により同年の他の上場株の利益や配当所得と相殺できます。
損失を含めずに計算すると利益のみに税金が課されるため、覚えておきましょう。
また、それでも損失が補えない場合は、翌年から最長3年まで損失を繰り越せる「繰越控除」も利用できます。
国税庁:損益通算・繰越控除
副業をしている場合
近年は、副業をするサラリーマンが増えています。
副業をしている場合は、確定申告の際に青色申告を行なったうえで下記の要件を満たすと、55万円(最大65万円)の所得控除を受けられる「青色申告特別控除」を利用できます。
| ・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること ・これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること ・上記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載して、確定申告期限までに申告書を提出すること |
加えて、①または②のいずれかを満たす場合は、65万円の控除対象です。
| ①事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存を行なっていること ②所得税の確定申告書や貸借対照表及び損益計算書等の提出を確定申告期限までにe-Taxを使用して行うこと |
なお、上記55万円または65万円の要件に該当しない方は、10万円の控除が適用されます。
国税庁:青色申告特別控除
不動産投資での節税対策が向いているケース

控除制度を利用するだけでなく、節税対策と資産形成を兼ねて不動産投資を行う方法もあります。
ただし、不動産投資には向き・不向きがあるため、よく理解したうえで検討しましょう。
年収1,200万円以上の場合は節税効果が高い
年収が1,200万円を超える方は、不動産投資による節税対策にも向いています。
なぜなら所得と税金の負担は比例するため、納税額が多いほど節税効果は高くなるからです。
反対に、年収が1,200万円以下の方は高い節税効果が期待できません。
また、不動産投資は所得税や住民税のほか、「贈与税」「相続税」の節税にも有効です。
資産の贈与や相続を考えている場合は、不動産投資を視野に入れるのもよいでしょう。
不動産投資で節税効果が得られる仕組み
不動産投資での節税対策は、減価償却を利用して行います。
減価償却とは、経年により価値が減る資産の購入費を耐用年数で分割して計上することです。
たとえば、「購入費が5,000万円」で「耐用年数が47年」の建物を購入した場合は、以下の計算方法で減価償却費を求めます。
| 建物の購入費5,000万円÷耐用年数47年=1,063,829万円(減価償却費) |
減価償却費は実際に支払うわけではありませんが、経費として計上できます。
加えて、その他の管理費や水道光熱費、修繕費、固定資産税、借入金の利子、税理士費用、雑給なども経費に含められます。
そのため、不動産投資でマイナスが出れば「損益通算」により給与所得と相殺することで節税できる仕組みです。
ただし、不動産所得の金額の損失のうちで次のものは、損益通算の対象となりません。
| ・別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの ・不動産所得で必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する金額 |
また、当初の計画より入居者が決まらなかったり修繕・管理費がかかったりするなどのケースもあり、不動産投資は永久的な節税方法ではないことを理解しておく必要があります。
不動産投資での節税対策には確定申告が必要
確定申告は給与以外の所得が20万円を超える場合に必要な手続きのため、サラリーマン(会社員)は馴染みのない方も多いでしょう。
しかし、不動産投資での収入が20万円未満の場合でも、「青色申告特別控除」を利用するには確定申告が必要です。
自分で手続きができるか不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
サラリーマンが会社設立で節税できるケース
以下のようなケースに当てはまるサラリーマン(会社員)は、会社設立によって節税できる場合があります。
| ・副業により事業所得がある ・不動産投資により不動産所得がある ・資産運用により所得がある ※株、FX、暗号資産(仮想通貨) ・相続材対策として会社を設立する など |
給与所得以外の所得があるケースに限られるため、給与所得のみの一般的なサラリーマンは会社を設立しても節税はできません。
なお、給与所得以外に所得があるケースでも、必ずしも会社を設立すべきとも言い切れません。
個人事業主として確定申告を行うことで節税できる場合もあるため、まずは税理士に相談し、慎重に検討する必要があります。
法人化による相続税対策は、以下の記事で詳しく解説しています。
相続税対策に有効な法人化を税理士が解説
サラリーマンが節税対策するときの注意点
サラリーマン(会社員)が節税対策する場合、注意すべきポイントを押さえておくことで、より高い節税効果が期待できます。
源泉徴収だけでは利用できない制度がある
サラリーマンの場合は会社が年末調整をしてくれるため、確定申告が必要でないケースがほとんどです。
ところが、会社の源泉徴収だけでは、一部の所得控除しか利用できません。
たとえば、以下の控除は自分で確定申告をした場合のみ利用できます。
| ・医療費控除 ・セルフメディケーション税制 ・特定支出控除 ・寄附金控除(ふるさと納税など) ・住宅借入金等特別控除 ・雑損控除 |
共働き世帯では収入の高いほうが扶養控除を利用する
共働きの夫婦は、収入の高いほうが扶養控除を利用しましょう。
扶養控除を利用する場合、所得金額が高いほど控除できる金額を増やせます。
扶養控除は、会社から年末調整の書類とともに渡される「扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入・提出しましょう。
過度な節税対策で支出を増やしすぎない
節税対策のためとはいえ、やみくもに支出を増やすのは得策ではありません。
控除限度額が設けられているものに、限度額以上の支出があったりしては無意味です。
支出とのバランスを考慮しながら、節税対策を行なってください。
【Q&A】サラリーマンの税金対策でよくある質問
ここからは、サラリーマンの節税対策でよくある質問にお答えします。
サラリーマンの節税対策は年収いくらから?
サラリーマンの節税対策は、年収680万円からを目安にするとよいでしょう。
令和7年度から大幅な所得税の改正が適用され、基礎控除や給与所得控除の額が変わります。
テレビや新聞で話題になっていた、給与所得者(サラリーマンやアルバイト、パートさん)に対して所得税が課税される最低限の金額である「年収の壁」が従来の103万円から160万円まで引き上げられることとなりました。
サラリーマンやパート・アルバイトの方でも160万円を超えると所得税が課せられますが、年末調整で会社に税の控除を申告すれば所得税は減額されます。
ここでポイントになるのが、サラリーマン等の方に対象となる所得税は超過累進税率が採用されており、年収680万円の辺りから負担率が高くなるといえることです。
超過累進税率で税率が10%から20%になる境がサラリーマンでいうと680万円の辺りにあります。
年収680万円のサラリーマンであり所得金額が330万円を超えると、税率が10%から20%になり、税負担が増えたと感じられる方も多く見受けられます。(※)
そこで、積極的に所得控除や税額控除の制度を使うのもよいかと思います。
(※京都府在住の40歳未満の独身で、月収40万円、ボーナス200万円のケースを想定)
サラリーマンが節税できる最強の裏ワザは?
残念ながら、裏ワザのような節税対策はありません。
控除制度を正しく活用することが最も節税に効果的と言えます。
サラリーマンがグレーな節税対策をするとどうなる?
節税対策の中にはグレーな手法もありますが、冒頭でもお伝えしたように税法の範囲を超えた脱税行為は犯罪になります。
節税と脱税の境目を誤ると大きなリスクを負うため、困ったときは税理士に相談しながら安全に取り組みましょう。
年収2,000万円のサラリーマンにおすすめの節税対策は?
年収2,000万円のサラリーマンの節税対策は、ふるさと納税やiDeCoがおすすめです。
ふるさと納税は寄附金控除が受けられるうえに、美味しいものを味わえたり、楽しい経験をすることができたりで、返礼品の種類も多種多様となっています。
また、iDeCoは老後資金を蓄えながら所得税や住民税の控除が受けられます。
ただし、ふるさと納税の返戻金は一時所得とされています。
一時所得の特別控除額は最高50万円であり、1年間の返戻品の額が原則として50万円を超えると所得税の課税関係が生じるので注意が必要です。
また、iDeCoは株価に影響を受けます。
2025年の春頃に「トランプショック」で冷や汗をかかれた方もいらっしゃったようです。
リスクがあり、短期の損益でなく長期の運用を目的としたものであるため、株価の下落があったときにもそれを受け止める心構えが必要かもしれません。
個人・法人の節税対策に関するご相談は「税理士法人吉本事務所」へ

税金や確定申告などに関するお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください!
当事務所では、個人のお客様から法人のお客様まで幅広いご相談・ご依頼をお受けしており、お客様のご状況に応じてベストな節税対策をご提案いたします。
また、同じオフィスに税理士、社労士、行政書士、保険外交員が在籍しているため、会社設立や起業・開業の際も総合的なサポートが可能です。
まずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
公式サイトはこちらから
相談予約フォームへのお問い合わせはこちらから

まとめ
サラリーマン(会社員)の所得税は、所得から所得控除を差し引いた金額に税率を適用して計算されます。
そのため、サラリーマンが手取りを増やすには、課税の対象となる所得を小さくすることが重要です。控除制度にはさまざまな種類があるため、まずは「自分が該当する制度はないか」を見直してみましょう。
なお、控除制度を利用するには「確定申告」が必要なものもあります。
自分で手続きができるか不安な場合は、税理士に相談してみましょう。
