【借地権は相続税の対象】相続税評価額の計算方法や相続手続きを税理士がわかりやすく解説
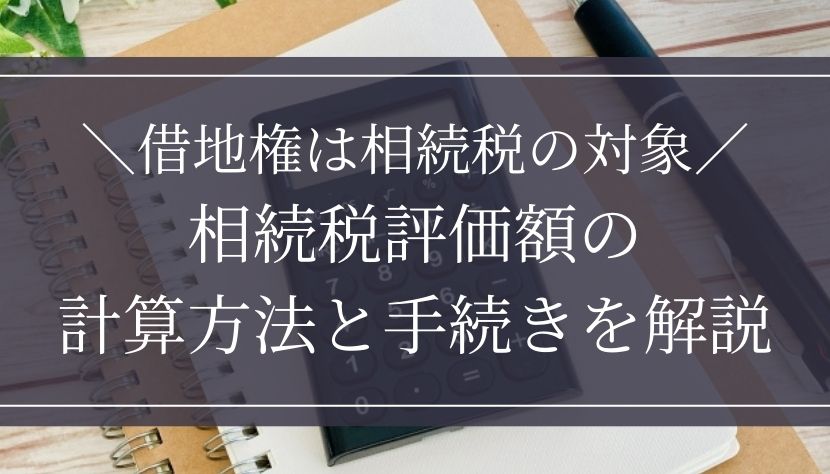
借地権は相続税の対象になるため、相続税がかかる場合があります。
他の財産と同じように相続税評価額の計算が必要です。
本記事では、借地権の相続税評価額の計算方法や相続手続きをわかりやすく解説します。
借地権を相続するときの注意点も解説しているので、トラブルを防ぐためにもお役立てください。
 | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 1973年生まれ 法学修士。1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
借地権を相続すると相続税がかかる
借地権とは、建物を所有するために地主から借りた土地を利用する権利のことです。
あくまで借主は土地を借りている状態ですが、借主が死亡すると借地権は借主の相続財産として相続税の対象になり、相続税がかかる場合があります。
とはいえ、相続税は借地権を含めた相続財産の合計額に対してかかる(=借地権のみの相続税は個別に計算できない)ため、借地権を相続したから必ずしも相続税がかかるとは限りません。
相続税がかかるかどうかは、すべての相続財産の相続税評価額を計算したうえで判断します。
<ポイント!>
相続税評価額とは、相続税を計算するための財産の価額のことで、財産の種類によって計算方法が決められています。
財産の種類(たとえば、現金、建物、借地権など)ごとに相続税評価額を計算し、相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかります。
反対に、相続財産の合計額が基礎控除額を超えなければ相続税はかかりません。
今すぐ税理士に相談したい場合は、税理士法人吉本事務所までお問い合わせください。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

借地権の種類
借地権は主に「普通借地権」と「定期借地権」に分かれます。
大きな特徴としては普通借地権は契約を更新できるため、地主側に正当な理由がない限り、借主側が希望すれば契約を更新し続けられます。
契約が満了したタイミングで地主に建物の買い取りを請求することもできます(定期借地権よりも借主の権利が強い)。
一方、定期借地権は契約を更新できないため、一定の期間で原則として地主に土地を返さなければなりません(普通借地権よりも地主の権利が強い)。
また、定期借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類に分かれます。
それぞれの違いをまとめると以下の通りです。
| 借地権の種類 | 存続期間 | 契約更新 |
| 普通借地権 | 30年以上 | あり |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | なし |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | なし |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | なし |
借地権の相続税評価額の計算方法
借地権の相続税評価額は、普通借地権と定期借地権で計算方法が変わります。
ここからは、それぞれの相続税評価額の計算方法を解説します。
普通借地権の相続税評価額
普通借地権の相続税評価額は、以下で計算します。
| 自用地とした場合の土地の価額×借地権割合=普通借地権の相続税評価額 ※自用地=自分が自由に利用できる土地 |
自用地とした場合の土地の価額は、路線価方式または倍率方式で計算が必要です。
路線価(道路に面する土地の1㎡あたりの評価額)が決められている場合は路線価方式で、決められていない場合は倍率方式を使います。
また、借地権割合は60~70%が一般的ですが、地域によって差があります。
土地の価額を計算するための路線価、倍率、借地権割合は、国税庁の財産評価基準書で確認できるため、自分で確認したい方は調べてみてください。
国税庁:財産評価基準書
定期借地権の相続税評価額
定期借地権の相続税評価額は、以下で計算します。
| 自用地とした場合の土地の価額×(A÷B)×(C÷D)=定期借地権の相続税評価額 A=定期借地権を設定したときの借主に帰属する経済的利益の総額 B=定期借地権を設定したときの宅地の通常の取引価額 C=相続が発生したときの定期借地権の残存期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率 D=定期借地権の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率 |
基準年利率と複利年金現価率は、国税庁の法令解釈通達で確認できます。
国税庁:令和6年分の基準年利率について
なお、上記は定期借地権を設定したときと相続が発生したときの借主に帰属する経済的利益に変化がなく、課税上の弊害がない場合の計算方法です。
特に定期借地権の相続税評価額は計算が複雑になるため、困ったときは税理士に相談することをおすすめします。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

借地権にかかる相続税の計算方法
冒頭でも触れたように、借地権を含めた相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかります。
基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
| 3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額 |
法定相続人が1人のときは3,600万円、2人のときは4,200万円、3人のときは4,800万円になります。
たとえば、法定相続人が2人で基礎控除額が4,200万円のときは、相続財産の合計額が4,200万円を超えると相続税がかかる仕組みです。
なお、相続税は以下の手順で計算します。
| 1.課税価格を計算する →相続税の対象となる財産から被相続人の債務と葬式費用を差し引く 2.課税遺産総額を計算する →課税価格から基礎控除額を差し引く 3.相続税の総額を計算する →課税遺産総額を法定相続分で相続したと仮定して計算する 4.相続人ごとの相続税額を計算する →相続税の総額と実際に相続する割合で再度計算する 5.各法定相続人の納税額を計算する →相続税額から基礎控除以外の控除額を差し引く |
基礎控除額や相続税の計算方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
相続税の計算方法を税理士が解説
相続税がかかると思われる場合や不安な場合は当事務所へお気軽にご相談ください。
\相続専門の税理士が在籍/
相続税のご相談は
初回無料の税理士法人吉本事務所へ

借地権を相続するときの手続き
借地権は相続財産として扱うため、借主が死亡すると法定相続人は借地権を相続できます。
結論から言うと、借地権の相続に名義変更は不要ですが、借地上の建物の名義変更は必要です。
ここからは、借地権を相続するときの手続きを解説します。
借地権の相続は名義変更が不要
先述の通り、借地権を相続するときは名義変更が不要です。
地主に連絡して「借主が亡くなり借地権を相続する」旨を伝えれば、地主の承諾も承諾料も不要です。
もし地主に「借主が死亡したなら土地を返してほしい」と求められても従う必要はありません。
ただし、稀ではありますが、借地権が登記されている場合は名義変更が必要となります。
<注意!>
相続ではなく遺贈(遺言によって法定相続人以外の人が財産を引き継ぐ)の場合は、地主の承諾と承諾料が必要となることを覚えておきましょう。
承諾料は、一般的に借地権価格の10%程度が目安です。
建物の相続は名義変更が必要
借地権の相続に手続きは不要ですが、借地上の建物を相続するときは名義変更が必要です(相続登記)。
不動産を相続したときは、取得を知った日から3年以内に名義変更をすることが義務付けられています。
なお、借地上の建物と借地権の相続人は同一にしましょう。
借地上の建物と借地権を分けて別の相続人が相続すると、第三者に借地権を主張できなくなるリスクがあるためです。
不動産の名義変更の手続きは、司法書士に依頼できます。
借地権を相続するときの注意点
借地権を相続するときは、トラブルを防ぐためにも以下3点に注意しましょう。
兄弟で借地権の共有は避ける
借地権は他の相続人と共有として相続することもできますが、将来的に借地権を売却したり建物の建て替えなどをしたりするときに共有者全員の合意が必要となります。
また、次の相続が発生すると権利関係が複雑になり、たとえ兄弟での共有でもトラブルが起こりかねません。
よって借地権の共有は避け、単独で相続することをおすすめします。
建物の建て替えや売却には地主の承諾がいる
建物の建て替えや増改築したり売却したりするときは、地主の承諾が必要です。
土地賃貸借契約書に承諾を得ることが記載されている場合があり、自己判断で進めてしまうと契約違反になる可能性があります。
なお、承諾を得るときは承諾料が必要で、建て替えや増改築は更地価格の3~5%程度、売却は借地権価格の10%程度が目安です。
相続税の控除や特例の要件を確認する
土地を相続するときは、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を使うことができます。
小規模宅地等の特例とは、簡単に説明すると土地の相続税評価額を減額できる(=相続税を軽減できる)制度で借地権を相続するときも対象です。
ただし、細かい要件が設定されているため、他にも相続税の控除や特例で使えるものはないかの判断も含めて税理士に相談するとよいでしょう。
借地権の相続や相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ

・何が相続税の対象になるかわからない
・相続税がかかるかわからない
・相続税がいくらかかるか知りたい
・相続税を減らすにはどうしたらよいか
などのお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください!
借地権は相続税の対象になるため、正確に相続税評価額を計算し、結果として相続税がかかる場合は相続税対策の検討も必要です。
当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、長年の経験と最新の知識を活かした相続税対策を強みに、相続税の申告まで一貫してサポートいたします。
わからないことや相続への不安を解消できるように私どもが丁寧にお応えいたしますので、どうぞご安心ください。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続の手続きやお悩みにも幅広く対応可能です。
相続税のご相談は初回無料でお受けしていますので、些細なことでもまずは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所の相続に関する業務の詳細はこちらから
お見積り・ご相談フォームへのお問い合わせはこちらから
\相続税のご相談は初回無料で承っております/

まとめ
借地権を相続し、相続財産の合計額が基礎控除額を超えると相続税がかかります。
相続税評価額の計算方法は、普通借地権か定期借地権かで変わり、特に定期借地権の評価は複雑です。
困ったときは税理士へ相談しながら、無理せずに相続の手続きを進めていきましょう。
